公開日: |更新日:
住宅性能を左右するUA値・C値・Q値。住まいづくりを考えている方の中には、この3つの数値が具体的に何を表しているのか分からない、という方も多いかもしれません。
このページでは、UA値・C値・Q値のそれぞれについて、概要や目安を詳しく解説しています。
UA値とは「外皮平均熱貫流率」の略称であり、簡単に言えば、「熱がどれだけ家から逃げやすいか」を表す数値です。このUA値が少ないほど、断熱性能が高い家であることを意味します。
UA値は、「熱損失量の合計÷延べ外皮面積」で求めることが出来ます。
断熱性能というと冬の暖房効率を連想しがちですが、実はUA値は夏の冷房効率にも関わっています。UA値が高い家は、暖かい飲み物は暖かく、冷たい飲み物は冷たく保つ魔法瓶のように、冬には暖気を、夏には冷気をキープすることが出来るからです。
C値とは「相当すき間面積」を略したものであり、「1平方メートルに存在する隙間の数」を表す数値です。このC値が大きければ大きいほど、「隙間が多く、気密性が低い家」となります。反対に、C値が少なければ少ないほど、「隙間が少なく、気密性が高い家」となります。
C値は「住宅全体の隙間の合計面積÷延べ床面積」で決まります。
高い断熱性は、高い気密性なくしてはありません。UA値と同様、C値は住宅性能を考える上で欠かせない数値です。
Q値とは、「熱損失係数」の略であり、UA値と同じく「熱の逃げやすさ」を表す数値です。UA値は熱損失量の合計を延べ外皮面積で割って算出するのに対し、Q値は「各部の熱損失量と換気による熱損失量の合計」を延べ床面積で割って算出します。
延べ床面積を使って割り出すQ値は、住宅の大きさや形状によって数字が変動します。そのため、UA値が主流となった現在では、Q値はあまり使用されていません。
UA値の目安は断熱等級で定められており、「ZEH基準」とされる断熱等級5を満たす値であれば十分なUA値と言えます。さらに「HEAT20G2」相当の断熱等級6および「HEAT20G3」相当の断熱等級7を満たす数値であれば、文句のない断熱性能と言えます。
ただし、断熱等級6以上を目指すとなるとかなりコストがかかります。コストパフォーマンスを考えると、断熱等級5相当のUA値を目指すのが、最も現実的かつバランスが良いと言えるでしょう。
なお、断熱等級4は「省エネ基準」とされていますが、実はそこまで厳しい基準ではありません。そのため、断熱等級4を満たしているからといって断熱性能が高いとは限らないので注意が必要です。
なお、北海道の住宅と関東地方の住宅とでは求められる断熱性能が異なるように、一口に断熱等級5といっても、住んでいる地域によって求められるUA値の目安は異なります。それぞれの地域ごとに断熱等級5で求められるUA値をまとめると、
となります。
※参照元:BE ENOUGH|断熱等級5を推奨!UA値の基準値と断熱性能の上げるために抑えるべき点を徹底解説!(https://be-enough.jp/blog/important/p7445/)
平均的な住宅の場合、C値は10cm2/m2程度が普通ですが、高気密性住宅の場合、1.0cm2/m2以下のC値が一般的です。また、中には0.5cm2/m2以下のC値を持つ住宅もあります。
C値は「1平方メートルに存在する隙間の数」を表す数値ですが、1.0cm2/m2のC値の場合、住宅の中にはがき約1枚分ほどの隙間しかないことになります。
※参照元:コノイエ|ハウスメーカー25社のC値・Q値・UA値一覧(https://konoie.kaitai-guide.net/housemaker-qchi-cchi/)
現在ではあまり使われないQ値ですが、Q値の目安についても確認しておきましょう。
断熱性の高い家を目指すのであれば、Q値は1.6以下が一つの基準となります。さらに、1.0以下のQ値であれば理想的であると言えます。Q値は建物の大きさによって数値に影響が現れるため、正確な断熱性能を測る場合に不向きとされています。建物の大きさに左右されない、UA値などを主に参考とするとよいでしょう。
UA値は「ZEH基準」とされる断熱等級5を満たす値(北海道で0. 4以下、関東地方~九州地方で0.6以下)が、C値は1以下が一つの目安となります。
では、断熱等級6以上相当のUA値や0.5以下のC値を目指す必要はないのでしょうか?
一般論として、断熱性能や気密性能を上げるための工事や建材は、性能が上がるにつれてコストパフォーマンスが悪くなります。同じ費用を出すのであれば、コストパフォーマンスが悪くなり始めるギリギリの段階でUA値・C値対策を止め、その分の費用を換気性能や耐震性能といった別の住宅機能に振り分けた方がより賢いと言えるでしょう。
UA値は、見積書に「UA値○○以下」と記載があるので、そこで確認することが出来ます。UA値について希望がある場合には、契約前のこの段階で伝えておきましょう。契約後に伝えると追加料金が発生します。
また、工務店・ハウスメーカーの担当者にUA値について直接尋ねてもいいでしょう。住んでいる地域ごとのUA値の目安を確認し、担当者に相談しながら、よりよい家づくりを目指しましょう。
関連ページ
家を建てるうえでママさんが気になることはたくさんあると思います。 長く安心して住みたいからアフターフォローが充実していてほしい、なるべく価格を抑えたい、寒い地域なので住みやすさ(暖かさ)を重視したいなど様々です。 そこで今回は岩手県の注文住宅会社の中からか各ニーズに対応した注文住宅会社を3つ紹介します。
選定基準:Googleにて「岩手 注文住宅」で検索し、10P内に表示された企業40社が調査対象(2023/12/20時点)。 その中から「保証を重視するなら」「価格を重視するなら」「住みやすさを重視するなら」の3つに分けておすすめを紹介。

引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/kids/kids001/
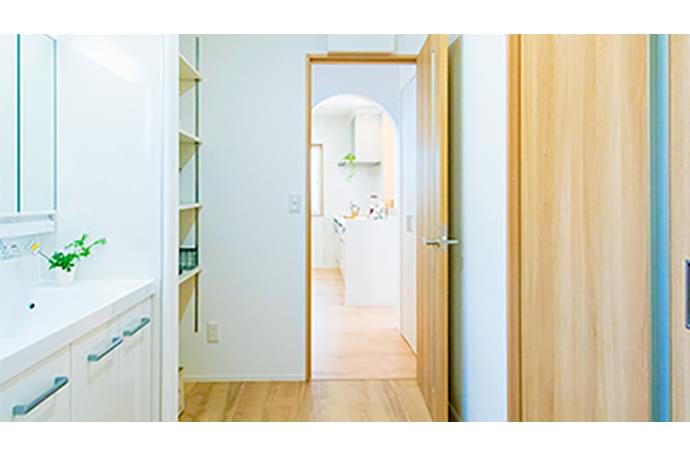
引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/mamaraku/

引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/order/
※1 例)38.7万円/坪で本体価格2,000万円の建築実例あり
参照元:SUUMO(https://suumo.jp/chumon/tn_iwate/rn_palcohome/149539_0001/jitsurei/jc_0004/)

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/12973/

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/9027/

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/1096/
※2 例)74.4万円/坪で本体価格3,499万円の建築実例あり
参照元:SUUMO(https://suumo.jp/chumon/tn_iwate/rn_hokushuhousing/501345_0001/jitsurei/jc_0004/)

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=46/#block98-46

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=43/#block98-43

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=34/#block98-34