公開日: |更新日:
建築物省エネ法の改正により、2025年4月以降に建てる住宅は省エネ基準を満たさなければなりません。そこで、住宅の省エネ基準適合義務化やZEH基準の家について解説します。
2022年6月13日に改正建築物省エネ法が可決したことにより、省エネ基準の適合義務化も決定しました。2025年4月に予定されている施行日以降に建築される住宅は、国が定めた省エネ基準に適合する必要があります。
そもそも従来の住宅建築では、省エネ適合は義務化されていませんでした。しかし、脱炭素社会を実現するため、省エネ基準を段階的に引き上げることが決定されたのです。
省エネ基準がなかった以前をスタート地点として、2025年の省エネ基準適合義務化が2つ目の段階。そして2030年にはZEH水準の省エネ住宅が最低ラインとされ、最終的には太陽光パネル付の省エネ住宅へと基準が変わっていく見通しです。
省エネ基準適合義務化によって、原則すべての新築される住宅や非住宅には、基準に適合して建てる必要が生じました。
改正法が施行される2025年4月までは、一部の建築物にのみ、省エネ基準の適合が義務付けられている状態です。たとえば、300m2以上の大・中規模非住宅の場合は、省エネ基準を満たさす必要があります。しかし、その他の住宅や非住宅には適合義務がなく、届け出義務や説明義務といった分類がされているだけです。
しかし、2025年4月の施行日以降に工事に着手する建築物は、一般住宅も省エネ基準を満たさなければならず、基準を満たしていない場合には着工も引き渡しもできません。
なお、政令で定める規模(10m2以下の想定)の建築物や、現行法で適用除外となっている建築物については、適合義務の対象から外れます。
「新築される建物が省エネ基準を満たしているか」は、建築確認手続き中にチェックされます。
まず、建築主は建築確認申請とともに「省エネ性能確保計画」を提出します。それをもとに行政が「省エネ適合性判定」を行い、「適合判定通知書」を発行。そして通知書を建築主事または検査機関へ提出し、省エネ基準適合確認が行われる流れです。なお、竣工時にも省エネ基準適合の確認が行われるケースもあります。
もしも省エネ基準適合確認によって適合が認められない場合や、手続きや書面に不備がある場合、確認済証や検査済証が発行されません。すると工事に着手できなくなったり、引き渡しが遅れる可能性があります。
2030年には、住宅や非住宅の省エネの最低ラインがZEH基準になるといわれています。2025年4月の省エネ基準適合義務化は脱炭素社会を目指した取り組みのひとつであり、以降も省エネの最低ラインを引き上げていく予定なのです。
2025年当時の基準で建てた省エネ住宅が、2030年のZEH基準には適合せず、資産価値にも影響を及ぼす可能性があります。2025年から2030年のZEH基準まで、5年間しかありません。そのため、これから新築住宅を建てようと考えている方は、ZEH基準の家を建てることをおすすめします。
2025年4月に適合義務化が生じる省エネ基準では、「住まいの熱を快適にコントロールできる」「住まいのエネルギーを賢く使える」という点を基準としています。つまり、窓や外壁の性能や設備機器等の一時エネルギー消費量を評価しています。
一方、ZEH基準の家は、「生活で消費するエネルギーよりも、生み出すエネルギーが上回ること」をさしています。省エネであることは共通していますが、ZEH基準の家では太陽光発電による電力創出や省エネルギー設備の導入、外皮の高断熱利用などによって、エネルギー収支をゼロ以下にすることを目指す住宅です。そのため、省エネ・断熱・創エネの3点を重視してつくられているのが特徴です。
ZEH基準の家は、省エネ設備を導入しているうえ、断熱性も確保しています。そのため、ムダな電力消費を抑え、光熱費を削減することができます。また、太陽光発電システムを導入していれば、電力をつくりだすことも可能。余剰電力が生じた場合、売電によってある程度の利益を得ることもできるでしょう。
太陽光発電システムに加えて蓄電池も設置すれば、発電した電力を蓄えておくことができます。停電や災害などの非常時にも電力を使うことが可能。電気自動車の充電も行えます。
ZEH基準の家は、BELSという住宅性能の認証制度において高評価を得られます。そのため、ZEH基準の家は資産価値が高くなりやすいといわれています。
ZEH基準の家は気密性や断熱性を高めているため、寒い冬でも室内が暖かいのが特徴。そのため急激な温度変化を感じにくく、ヒートショックや心筋梗塞、脳卒中などの発症リスクを軽減できます。
参照元:国土交通省|2025年(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます[PDF]
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519931.pdf)
参照元:国土交通省|待って!家選びの基準変わります[PDF]
(https://www.mlit.go.jp/common/001582580.pdf)
関連ページ
家を建てるうえでママさんが気になることはたくさんあると思います。 長く安心して住みたいからアフターフォローが充実していてほしい、なるべく価格を抑えたい、寒い地域なので住みやすさ(暖かさ)を重視したいなど様々です。 そこで今回は岩手県の注文住宅会社の中からか各ニーズに対応した注文住宅会社を3つ紹介します。
選定基準:Googleにて「岩手 注文住宅」で検索し、10P内に表示された企業40社が調査対象(2023/12/20時点)。 その中から「保証を重視するなら」「価格を重視するなら」「住みやすさを重視するなら」の3つに分けておすすめを紹介。

引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/kids/kids001/
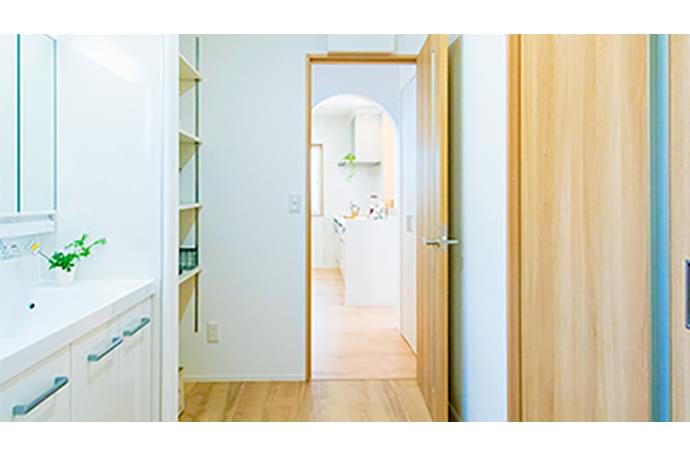
引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/mamaraku/

引用元:パルコホーム公式サイト
https://www.palcohome.com/project/order/
※1 例)38.7万円/坪で本体価格2,000万円の建築実例あり
参照元:SUUMO(https://suumo.jp/chumon/tn_iwate/rn_palcohome/149539_0001/jitsurei/jc_0004/)

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/12973/

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/9027/

引用元:北洲ハウジング公式HP
https://www.hokushuhousing.co.jp/case/1096/
※2 例)74.4万円/坪で本体価格3,499万円の建築実例あり
参照元:SUUMO(https://suumo.jp/chumon/tn_iwate/rn_hokushuhousing/501345_0001/jitsurei/jc_0004/)

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=46/#block98-46

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=43/#block98-43

引用元:北日本ホーム公式サイト
https://kitanihonhome.com/publics/index/27/detail=1/b_id=98/r_id=34/#block98-34